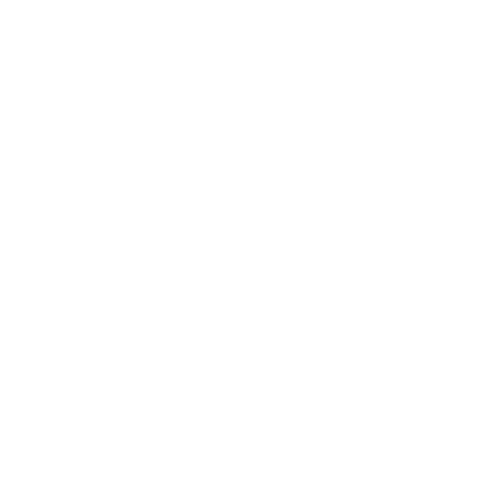Digital content
as physical
communication.
消費の渦の中で、デジタルも長く愛されるものを
デジタルコンテンツの生産においては制作ツールの普及にAI技術が相まってより一般的なものになり、プロモーション活動なども以前より軽やかになりました。それはSNS主流の情報環境(リアルタイムの伝達)に相性がよく、プロに依頼しなくてもライトなものなら完成まで「作りながら考える」作業をも可能にしています。
「量」が必要な場面もありますが、技術の一般化は最低限の品質を引き上げているという見方もあります。
立ち返るべきは、それはオープンソース的な技術供給の功績で、使い手(時にブランド・ベンダー等)にとって重要なことは相変わらず「商品=メッセージ」の担保であることです。そして、デジタルも大小関わらず作る・消費する「モノ」となり、すべてが媒介としてコミュニケーションの性質を持っているということです。
大きなプロジェクトとなれば、コンサルティング・広告プランニング・コンテンツの企画・制作と、ブランディングやマーケティングの目的に対して各専門事業者がギアのように伝導し、一貫したコミュニケーションの基礎・信頼を築くことで高い品質を維持します。
対して有効な情報伝達にリアルタイム性が強くなったことで、SNS投稿などの細やかな動きの重要性が高まる一方で、クリエイティブにムラが出てイメージが乖離してしまったり、逆にブランドイメージを守るために停滞してしまったりというケースを目にします。
また、小規模プロジェクトやスタートアップは元手に限りがあれば販促先行になる傾向が見えますが、デジタルプロモーションも短期や低コストで生産できるものはおおよそ消費も早いので、これだけでは手を動かし続けるほかありません。
表面上のコミュニケーションに気を取られると、ブランド毀損を招く可能性も出てきます。
かけた時間、大きさ、人数に関わらず、手塩にかけて育てた商品やサービスには普遍的に価値があるはずです。
それらがヒトに価値づき、長くを共にするために、デジタルコンテンツというモノ・コトに相応の見方をすべきで、より良いコミュニケーションを築けると考えています。
発信までが容易になったからこそ、ロードマップと照らして無駄なコストをかけないように必要性を吟味すること、目的に合ったチャネルとクリエイティブ、質と量のバランスと生産維持、そしてこだわるところに力を注ぐこと。
アールデパートメントのクリエイションは単一の機能評価はもとより、持続的価値、ブランドコミュニケーションを据え置いたパートナーシップのもとにあります。創造性、企画・効率性、耐久性を持ってワンチームでマーケットに臨めたらと思います。